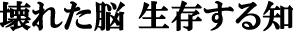 |
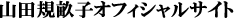 |
||
 |
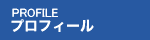 |
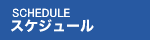 |
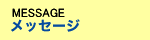 |
 |
 |
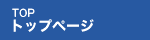 |
| 山田規畝子からみなさんへのメッセージです。 |
| 最新のメッセージ 2013年〜2016年 2011年〜2012年 2007年〜2010年 2006年後半 2006年前半 |
| 年末のご挨拶 | ||
|
高次脳機能障害関係者の皆様を始めとする山田規畝子オフィシャルサイトご来訪の皆様に年末のご挨拶です。 本年は暑い夏の間お休みをいただき、何とかご要望のあった沢山の地にお邪魔することができました。障害に負けず力強く日々を暮していらっしゃる当事者の皆さん、支えるご家族の皆さんに直接お会いすることができ、歓迎していただくことで何か人様のお役に立つことができたという喜びとともに、大きなパワーをいただきました。 これから寒い冬になりそうですが、高次脳機能障害に苦しむ皆様は、決して一人ではないという思いを当サイトでお持ちいただき、また明日に向かう力にしていただけたらこの上もなくうれしいことです。 来年は1月22日に東京での橋本圭司先生との対談講演を皮切りに、既に春場所講演のご依頼もいくつかいただいており、来年も元気に全国色々なところへ伺いたいと楽しみにしております。 2月には2冊目の著書の「それでも脳は学習する」の改訂版が「壊れた脳 生存する知」と同じく角川ソフィア文庫から文庫本として発売になります。さらに進化した山田規畝子の世界をご覧いただけると思います。ご一読いただければ幸甚です。 冬来たりなば、春遠からじ。 よいお年を。 |
||
| 山田規畝子謹白 | ||
| (2010.12.29) | ||
| 年末のご挨拶 | ||
|
今年も早、残すところ2週間になりました。一年間山田規畝子オフィシャルサイトにたくさんの方にお立ち寄りいただき、山田自身もたくさんのパワーをいただきました。また年間を通じて日本全国にお邪魔することができました。ご支援やお励ましを下さった方々に厚くお礼を申し上げます。 高次脳機能障害についての知識が少しでも世間一般の当たり前になって、当事者は社会の中で普通に暮らしやすく、一般の方は誰にも起こり得るこの脳の障害が自分や身の回りで発生した時いたずらに悩まず苦しまず落ち着いた対処ができるように、日本の常識として社会に認識されるように来年も微力ながら活動を続けていきたいと思います。 2010年の講演会の皮切りは2月の山田の出身地香川県でさせていただきます。春には東京・横浜など人口の多い地域にも参りますので、当サイトのスケジュールのページをお確かめの上、たくさんご参加いただきますようお願い申し上げます。 |
||
| 山田規畝子敬白 | ||
| (2009.12.18) | ||
| 神戸に行ってきました | ||
|
7月4日(土)、「認知運動療法研究会」の講演で神戸に行ってきました。 新しい考え方の高次脳機能障害の治療とそれに燃えている治療者の皆さんに接してきました。 600人とかのいわゆるリハビリの先生が集まっている会だったのでむんむんしてました。キーワードは認知運動療法という新しいやり方です。当事者が見ている不思議で困った世界を徹底的に本人にインタビューすることから始まる手法です。 誰かに言ってもどうせ興味も持ってくれないし、めんどくさいから黙っていようという時代は終わりました。 講演後、著書にサインをさせていただきました。たくさんの方と握手をしたり、直接お話を伺うことができ、有意義な時間になりました。みなさん、本当にありがとうございました。  著書にサイン中です。  著書もたくさんの方にお買い上げいただきました。  ほっとひと息の山田とマネージャーです。 掲示板に書き込みもしてくださっているしゃあさんよりお写真のご提供をいただきました。ありがとうございます。 |
||
| (2009.07.08) | ||
| 山田が本を書いたり当事者やそのご家族の方とお話をする機会を持つ目的 | ||
|
私の言いたいことはこれまで3冊書かせてもらった本にほぼまとめることができました。 最初の本は自分自身もまだいかにも病気であふあふしてた時の本です。 それから少し経って、これから何をしようかな、と落ち着いて考えられるようになって、ちょうど編集者さんが声をかけてくれた時にできたのが、その頃の普通の暮らしの中で考えたことをつれづれにエッセイに書いた2冊目でした。 それから少し間があって、自分が自己流でやってきたリハビリに少し違うリハビリの視点を与えてくれる人があったりで、実際リハの現場の方たちに全国あちこちの講演で出会ったりして、本当に高次脳機能障害リハビリのまっただ中にいる人たちが本当は何を知っていて何を知らないのかをやっと察することができるようになってきて、多分私のように高次脳機能障害って実際は何なのかを身をもって知っている者にしかわからないこまごましたことを老いて面倒臭さが増してしまう前に書いておかないといけないと思って、究極の答えとは断言できないまでも、今の私が思うリハビリや暮らしの事を遺産としてまとめたものが3冊目の「高次脳機能障害者の世界」という本です。 一生このままで治りませんよと言われた人々にネットや講演でたくさん出会い、一つにはどこかで脳が傷ついても大丈夫よ、と言ってあげる人間もいなくてはいけないのではないかと思うようになり、大丈夫という言葉自体あいまいで客観性に乏しいのですが、必要以上に悲観的になって苦しんだところで、苦しまなかった人より事態が良くなるわけではなく、無駄なストレスに無駄にエネルギーを吸い取られるほどばかばかしいことはないので、少なくとも会うことができる人たちには、私のような楽観主義者の姿を見てもらってまずはホッとしてもらえたら、という思いが強いのです。 いつも暗い未来を思って塞ぐ日々を送らなくてもいいのだ、と思ってもらいたいのが私の活動の一つの目的です。負ってしまった障害をしっかり抱えてそこにいるあなたが今のあなたであることを認めてしまい、だからできないものはできないのだ、と少し開き直ってみることができればこの世の物理学的なものは何一つ変わらなくても心はすうっと軽くなるはずでしょう。 、できないものはできないのだ何が悪い!と独り言を言ってみてください。それは絶望ではありません。今ありのままの自分を受け入れたというだけのことです。できない自分を受け入れたところで取って食われるわけじゃありません。 山田との対話の中や山田の書いた本で少しだけ心が軽くなったらそれが山田のやりたいことの全部です。山田は保険証を持ってかかりに行く医者ではなくなってしまいましたが、今山田にしかなれない医者でいることをとても幸せに思っています。大丈夫よーと言いながら。なるだけ楽しく元気で生きて行きましょう。そうしている間にも壊れた脳は元の形に戻ろうとしてます。1つ1つ細胞を作ってそのネットワークを広げて。そんな脳自分のの中で起っていることを想像してみてください。 |
||
| (2009.03.31) | ||
| 高次脳機能障害関係者のみなさんへ | ||
|
世の中にはいろんな脳の障害がありますが、高次脳機能障害のうれしいところのひとつは「進行性の障害ではない」というところです。事故なり卒中なり障害の原因となった状態が落ち着けば、個人差はあってもみんな、生きていればだんだん良くなること、治ってしまうというものではなくても時間の経過とともにだんだん良くなっていくのが普通です。 医者はそうやって誰かの一生の自然経過を全部観察してみたことがないので絶対良くなっていきますよと、太鼓判を押すことができないのです。だから多くの人はこれ以上良くならないというようなしどろもどろの説明を受けることになるんですが、それも無理からぬことなので責めないで上げてください。もしいいことばっかり言って結果が悪かったら、と思ってどうしても重めの説明をするのが医者です。 でもね、私を見てもらってわかるように脳の傷も良くなって行くのが普通です。薄皮を剥ぐように少しずつ少しずつ。今日より明日、今月より来月って必ず実感があるはずです。山田は最後の大きな出血から8年まだ治り続けています。少しずつ。 |
||
| (2008.10.17) | ||
| 高次脳障害について言いたかったこと | ||
|
テレビ番組等では私の認知機能について「○○の機能(たとえば言語,記憶等の機能)を失ってしまいました」という断定的で極端な表現をして感動的に演出しようとすることがありますが、高次脳機能障害の患者さんではそういった人間しか持たぬ高次の能力が普通では考えられぬほど弱体化するので、社会生活上困ったりするのですが、それは決して「失ってしまう」のではありません。私の本のタイトルの「生存する知」というのはその生き残った能力のことです。 その弱くなってしまった機能を維持発展させるために有効な訓練がリハビリテーションとしてあえて課せられなければ、それはやはり回復しないかより脆弱なものになってしまうわけです。そういう訓練の効果は少なくとも5年以上はあるものと思い、では、いつまでかというと、私が自分の例とこれまでにお会いした同じ障害の皆さんを見ていると、その機能の回復は生きている限りずっと続いていくように思われます。それが2冊目の本の「それでも脳は学習する」ということなのです。 毎日自分の鈍った、時には間違える感覚で社会に接し、試行錯誤を繰り返しながら生きている私の脳は、右側の大きな部分を一時は潰したようになっていても、今では右目で見たものを右脳に確かに記憶し、なくしてしまったかのように錯誤していた左半身の感覚を少しずつ思い出し始めている事を大きな脳損傷から7年も経つ今実感しています。メモも取らずに聞いた一ヶ月のスケジュールの日時を手放しで覚えていることができたり、一瞬の出会いで目に焼き付けた人の顔を何ヶ月も覚えていたりできますし、昔持っていた記憶に関して10年以上経って人の顔や名前や仕事上の専門用語や薬の名などをはっきりと再生することができます。 そういう残された力を更に高めたり、長く維持する可能性をリハビリテーションは持っています。あまり根拠のあると思えない日数の制限で、高次脳機能障害者からリハビリテーションのできる環境を奪わないで下さい。 |
||
| (2008.01.01) | ||
| 1年を振り返って | ||
|
いろんなとこで今年は時間が過ぎるのが早かったといわれますが、山田の一年もあっという間でした。やっと香川県外で講演をさせていただくのに体の方も慣れてきたところでしたが、今年は遠くは新潟までお呼び頂き、身近では四国全県にてお話しすることができ、お向かいの岡山でも玉野市と岡山市市に伺い、前者では500人もの聴衆に聞いていただき、岡山では岡山在住の大学時代の恩師にも来ていただき第二の人生(余生?)を生きている私の思いの丈を最前列で聞いていただき有難さに涙の出る思いでした。平均月一度の講演で200人〜300人の参加が標準的といったところでした。今年は特に関西からのオファーが多く滋賀県、大阪市内、姫路、堺、明石と幼馴染のマネージャーとおばちゃん2人の修学旅行のような楽しい道中でした。 11月の堺では600名、明石では1000名のご参加を頂き、高次脳機能障害の多くの当事者や関係者、いつもHPに来て下さる方々との対面と、やはり時に疲労し寄る年波を感じることもありましたが、お会いする皆さんにパワーを頂き、何とか今年計画分の講演予定をこなすことができました。おかげさまで体調を崩すこともなく、苦しかったのは抗癲癇薬副の副作用だけで、何とか体をだましだまし乗り切ることができました。どうも有難うございました。 来年も既に5月あたりまで予定が入っております。講演依頼の連絡をしたにもかかわらず山田の方から連絡がないとおっしゃる方はご面倒ですがサイトの方にでも結構ですのでご一報下さい。山田は元気そうにはしていてもやはり脳機能障害者です。忘れているということもよくあります。一度マネージャーに連絡のついている方は、マネージャーにご一報下さい。 各地で握手をした皆さんの手のぬくもりが心に残った1年間でした。最後に1月に放映された「壊れた脳」のテレビドラマ、2月に上梓した2冊目の著書、10月に発売になった漫画版「壊れた脳」などをごらんいただいた皆様有難うございました。山田は来年も高次脳機能障害を日本のジョーシキにするべく微力ながら頑張って行きたいと思います。ご協力いただける方はどんどんご協力お願いします。 また来年も山田規畝子オフィシャルサイトをよろしく。良いお年を。 |
||
| (2007.12.23) | ||
| 山田の願い | ||
|
高次脳機能障害は日本にどのぐらいいるのか。 国立リハビリテーションセンターの調べでは、全国に約27万人。18歳以上65歳未満に区切れば約7万人。普通に生活していれば身の回りに必ず何人かいてもおかしくない数なのである。山田の拙著「それでも脳は学習する」の中でよたろう(古典落語に登場するとぼけたキャラの若者。)高次脳障害者説を裏付ける数字でもある。高次脳機能障害は珍しい障害ではない、ということである。 誰もがいつ持ってもおかしくない障害であることを認識した上で、自分が、家族が、友達がこの障害を抱えても健常者と同じ社会の一員として当たり前に暮らせる社会であって欲しいというのが山田の願いです。 |
||
| (2007.04.20) | ||